2025年4月3日に米国が発表した「相互関税」政策は、世界の金融市場に大きな影響を与えています。特に日本に対しては24%という高い関税率が設定され(自動車には別途25%)、日本経済や市場への影響が懸念されています。これを受け、自民党金融調査会は4月15日に関係者からのヒアリングを行い、対応を協議しました。
金融市場の動揺と企業活動への影響
米国の関税発表と中国による報復関税の発表を受け、日本の株式市場は先週、乱高下しました。日経平均株価は3日からの5日間で1,000円前後の値動きが続く不安定な状況となり、特に金融関連株や輸出関連株の下落率が大きかったと報告されています。
市場の不安定さは、企業の資金調達計画にも影響を及ぼしています。長期金利の指標となる10年物国債の利回りも大きく変動しており、これを受けて大手企業の間では社債の発行を見送る動きが出ています。例えば、サッポロホールディングス(約500億円)、日清食品ホールディングス(約300億円)、サントリーホールディングス(約500億円の劣後債)などが、予定していた社債発行を見合わせました。いずれも新規発行の日程は未定となっています。長期金利の変動が長引けば、企業の資金調達戦略への影響がさらに懸念されます。
専門家・調査機関の見解
自民党金融調査会に出席した東洋大学の野崎浩成教授は、米国の関税政策がサプライチェーン全体に負の波及効果をもたらし、賃金などにも影響が及ぶ可能性があると指摘しました。また、個人投資家の投資マインドの低下や、年金資金運用が低リスク志向に回帰することへの懸念も表明されています。
大和総研は、相互関税の影響を踏まえ、日本、米国、欧州、中国の経済見通しを下方修正しました。日本の2025年の実質GDP成長率予測は、前回予測から0.4%ポイント引き下げられ、+1.0%となっています(米国は0.6%ポイント減の+1.1%、ユーロ圏は0.4%ポイント減の+0.7%、中国は0.6%ポイント減の+3.9%)。米国の関税政策や各国の報復関税の先行きには不透明感が強く、場合によっては米国が景気後退に陥る可能性も排除できないとしています。
政府・日本銀行の対応
日本政府は、事態の打開に向けて米国との交渉に臨んでいます。赤沢亮正経済財政・再生相は、関税交渉のため4月16日に訪米し、「可能な限り早期に成果が上げられるよう政府一丸となって取り組む」と述べています。日本側は、相互関税の上乗せ分が一時停止されている90日間に、関税の完全撤廃を目指して交渉を進めたい考えです。ただし、米国側の要求内容は明確でなく、決着は見通せない状況です。政府内では、交渉が長期化すれば7月の参院選に影響が出るとの懸念も出ています。なお、日本政府は交渉において、保有する米国債を交渉材料として利用する考えはないとしています。
日本銀行の植田和男総裁は、トランプ政権の関税政策について「政府と緊密に連携しつつ、引き続き市場動向と経済・物価への影響を十分注視していきたい」と述べており、今後の金融政策運営への影響も注目されます。
今後の展望
米国の関税政策は、日本経済および金融市場に大きな不確実性をもたらしています。今後の日米交渉の行方や、それを受けた市場の反応、企業活動への影響を引き続き注視していく必要があります。


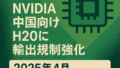
コメント